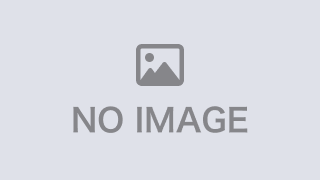- 投稿日:2025/08/12
- 更新日:2025/10/30

【転職活動記録 要約】
1.きっかけと準備
・2024年11月にリベシティへ入会し、家計管理やインデックス投資を実践。
・家計管理により、年収900万円でも生活可能と判断。年収よりも働き方改善を優先する方針を決定。
・両学長の「転職活動は価値確認になる」という助言を参考に、2025年4月4日に転職活動開始を決断。
2.エージェント活用
・JACリクルートメントを中心に活動。途中で別エージェントにも登録し、提案を比較検討したが、JACリクルートメントを優先。
・求人情報はExcelで整理し、重要項目を◯△×で評価。ChatGPTを活用して求人票内容の整理や比較表を作成。
・8社応募(書類選考通過6社)
3.面接準備と実施
・6社受験(オンライン2社・対面4社)。
・ChatGPTの音声対話機能で面接練習。
・面接記録をその日のうちに作成しエージェントへ提出。次の日の面接準備に活用。
4.企業選定の理由
・決定企業は役員・管理職の雰囲気が温かく、受け入れられる感触があった。
・定年は60歳または62歳だが再雇用制度あり。再雇用後も年収が大幅に下がらない点を重視。
・年収は現職と同等かやや上回る見込みで、働き方改革と年収維持を両立。
5.退職手続きと入社準備
・内定直後に上司へ報告。引き留めを受けたが最終的に円満退職。退職金もゲット。
・引き継ぎは自身の知識で対応。退職金税額の確認や企業型DC移管方法も検討。
6.総括
・家計管理を通じて年収への不安を減らし、働き方を重視できたことが成功要因。
・転職活動で得られた情報・経験は今後のキャリアにも活かせる。
【はじめに】
私は長年、あるインフラ系企業で勤務してきました。しかし近年、母の介護に直面することになりました。
現職では「転勤や長期出張の可能性があり、そうなると介護対応が難しくなるリスクがある」---この危惧が、私の将来設計を見直すきっかけとなりました。
まず着手したのは家計管理です。将来の年金額を試算し、生活費や資産運用を含めた長期的なシミュレーションを行いました。その結果、年収900万円まで下がっても十分生活が成り立つという確信を得ました。
これにより「年収を理由に転職を諦める必要はない」と判断でき、転職活動に踏み切ることができたのです。
結果的に、内定先からは現職とほぼ同額、むしろわずかに上回る年収を提示いただきました。加えて、働き方を見直すことで生活の質を保ちつつ、介護と仕事の両立を図れる見通しが立ったことは、私にとって大きな安心材料となりました。
第1章:リベシティとの出会いと転職活動の第一歩
将来への漠然とした不安を感じていたある日、私はYouTubeで「両学長」の動画に出会いました。資産形成や働き方、そして自由な人生設計について語るその内容に引き込まれ、気づけば関連動画を次々と視聴していました。その中で紹介されていたオンラインコミュニティ「リベシティ」に興味を持ち、思い切って入会しました。
リベシティに入ってからは、学びの幅が一気に広がりました。「守る力」「稼ぐ力」「増やす力」「使う力」「貯める力」という、お金に関する5つの力の全体像を知り、その中でも特に自分にとって重要だと感じたのは「守る力」「稼ぐ力」「増やす力」「貯める力」でした。ここから家計管理の重要性を再確認し、実際に自分の家計を徹底的に見直すことに着手しました。
まずは将来の年金見込額を調べ、現在の金融資産を正確に把握しました。次に、日常の支出と固定費を洗い出し、老後までの資金需要をシミュレーション。インデックスファンドを活用して、老後に備えた長期的な資産形成の重要性も理解しました。これらの過程で、「仮に年収が900万円に下がっても、十分に生活を維持できる」という確信を得ました。さらに、現職のように転勤や長期出張が続くと介護への対応が難しくなることも考慮に入れ、生活の質を維持しつつ働き方を変える必要性を実感しました。
こうして、綿密な家計管理と将来予測に基づき、「今このタイミングで転職しても生活基盤は揺らがない」という裏付けを得たうえで、私は転職活動に踏み切ったのです。
リベシティは、単なる情報収集の場ではありませんでした。同じように人生の舵取りを真剣に考える人々とつながり、実践的なアドバイスを得られる場でもありました。特に「転職チャット」では、
「転職エージェントは1社に絞らず、複数登録して比較するべき」
という助言をいただき、これが活動方針を大きく変えるきっかけになりました。
それまで私は、どこか一社に腰を据えてお願いすればよいと考えていました。しかし複数のエージェントとやり取りしてみると、対応スピード、提案の質、求人情報の鮮度に大きな差があることを実感。比較の重要性を痛感しました。
最終的に私が最も信頼できると判断したのは、JACリクルートメントのM氏でした。常に余裕を感じさせる落ち着いた対応で、私の希望条件や背景を深く理解し、的確な求人提案を行ってくれました。この方はおそらく社内でも高い実績を持つ方だと感じるほど、段取りと提案力が際立っていました。
こうして、「家計管理による安心感」と「複数比較で最適な担当者を選ぶ」という2つの軸が、私の転職活動の土台を築いていったのです。
第2章:転職活動の実務と戦略
家計管理と将来予測で「今、動いても大丈夫」という意思を固めた私は、転職活動の実務フェーズへと踏み出しました。
当初はJACリクルートメントにのみ登録し、担当のM氏から企業紹介を受けながら、各社の特徴や採用方針の説明を受けていました。M氏は、企業ホームページの組織図をもとに部署構成や人員構成までかみ砕いて解説してくださるなど、単に求人を紹介するだけではなく、私が企業文化や組織体制を正しく理解できるように丁寧な説明をしてくださいました。その姿勢からは、「自分が提案した企業に入ってほしい」という営業的な思惑よりも、「私の転職を成功させたい」という純粋なサポート精神が感じられました。
こうして順調に企業提案を受けていたのですが、ふと「このまま一社だけで活動していいのだろうか」という疑問が浮かびました。そこでリベシティの転職チャットで相談したところ、「複数のエージェントに登録し、それぞれを比較する方が望ましい」とのアドバイスを受けました。
この助言を受け、面接に進む前の段階で2社目の転職エージェントにも登録。そこからはJACともう一社の双方から企業提案を受ける形となりました。
両者の提案や情報を比較検討しましたが、最終的にはJACリクルートメントのM氏を優先して活動を進めることを決断しました。その理由は、M氏の提案力・情報量・説明の深さに加え、私の立場や条件を踏まえた現実的かつ戦略的な助言が他のエージェントよりも圧倒的に優れていたからです。
特に印象的だったのは、M氏が提案企業について説明する際、表面的な求人票や公式情報だけに頼らず、自身のネットワークや社内共有情報から得た“生きた情報”を交えてくれた点です。
企業の経営方針や部署間の力関係、現場の雰囲気までを含めた立体的な説明は、私の企業選びに大きく役立ちました。また、私の条件や将来像を理解したうえで、「この会社は年収面では少し劣るが、働き方の自由度が高い」「こちらは即戦力として迎えたい意思が強い」など、私が判断しやすい形に情報を整理してくれました。
結果として、転職活動においてはエージェントとの相性が極めて重要であると強く実感しました。自分に合ったエージェントと巡り合えれば、情報の質も交渉力も大きく向上し、活動全体の成果に直結します。私の場合、その相性の良さがM氏との出会いにあり、これが転職成功の最大の要因の一つになったと確信しています。
第3章:企業選びと面接への挑戦
複数のエージェントを活用しながら企業情報を集め、最終的にM氏を中心に活動を進めることを決めた私は、いよいよ具体的な企業選びに入りました。
提案された企業はどれもインフラ分野で一定の実績を持つ中堅から大手まで幅広く、勤務地や事業領域、将来性などの条件は多岐にわたっていました。
この段階で私が重視した条件は、次の順序でした。
1.勤務地が関西(特に大阪)に限定できること
2.過度な全国転勤や長期出張が不要であること(介護事情による)
3.自身の専門分野である鋼橋関連の経験を活かせること
4.定年後の再雇用条件が良いこと
4つ目については、「65歳まで必ず働けること」を最優先にしたわけではありません。むしろ、60歳や62歳でいったん区切りを迎え、その時点で今後の状況を見据えて再雇用していただけるかどうかを判断したいと考えていました。
再雇用制度があるだけでなく、その際の年収が大きく半減するのではなく、8割〜9割程度に抑えられる可能性が高い企業を優先したのです。こうした条件は求人票には明記されないため、エージェントとの情報共有が欠かせませんでした。
エクセルによる条件整理とChatGPTの活用
提案された候補企業の情報は、エージェントからの説明や求人票(PDF)に記載された内容をもとに、すべてエクセルで整理しました。
 私は自分が重視する条件を縦軸に並べ、各企業がそれを満たしているかを「〇・△・×」で評価する方式を採用しました。例えば、勤務地条件が完全に合致すれば「〇」、一部条件付きで合致すれば「△」、全く合致しなければ「×」という具合です。
私は自分が重視する条件を縦軸に並べ、各企業がそれを満たしているかを「〇・△・×」で評価する方式を採用しました。例えば、勤務地条件が完全に合致すれば「〇」、一部条件付きで合致すれば「△」、全く合致しなければ「×」という具合です。
求人票はPDFで届くため、そのままでは加工しにくい場合がありました。そこで、PDFからテキストをコピーしてChatGPTに貼り付け、重要なポイントを整理してもらう方法を取りました。
具体的には、「この求人の勤務地条件と再雇用制度の詳細を抽出してください」「この企業の事業分野と過去の実績を要約してください」といった形で依頼し、私の判断に必要な情報だけを短時間で抽出できるようにしました。
こうした情報整理を重ねた結果、最終的には10社に応募する方向で検討し、企業ごとの優先順位を明確化することができました。
面接準備と戦略
面接対策については、M氏から「面接は情報提供の場ではなく、双方の相性確認の場」というアドバイスを受け、形式的な受け答えではなく、企業が求める人物像と自分の経験をどう結びつけるかを中心に練習しました。
この練習では、ChatGPTの音声でリアルタイムにやり取りする機能を活用しました。実際の面接のように、質問が音声で飛んできて、それに対して自分の声で答える形式を繰り返すことで、想定問答集の内容を自然に口から出せるようにしました。回答の言葉選びや間の取り方も、音声練習を通じて改善することができました。
実際の面接は、6社のうち2社がオンライン、4社が対面という構成でした。
オンライン面接ではTeamsやZoomを用い、画面越しでも表情や声のトーンに注意を払いながら受け答え。対面面接では、面接官の反応を直接感じ取れるため、より具体的なエピソードを盛り込みつつ、相手が興味を持った部分を深掘りして話すように心がけました。
面接本番での印象的なやり取り
面接本番では、企業ごとに雰囲気や質問の傾向が大きく異なりました。ある企業では、私のこれまでの施工計画経験を非常に高く評価し、「その知見を若手育成にどう活かすか」を深く掘り下げられました。別の企業では、現場から上流工程へのキャリアチェンジについて、リスクや覚悟を問う厳しい質問が続きましたが、想定問答で準備していた内容を軸に、落ち着いて応答できました。
また、公共事業比率の高い企業では、「地域に根ざした技術貢献」をどう考えるかという価値観的な質問があり、自分の介護事情や地域貢献への想いと絡めて答えることで、面接官の表情が和らいだ場面もありました。
面接記録の作成と効率的なサイクル
さらに、M氏から「面接記録(議事録)を作ってほしい」と依頼を受けました。これは、おそらく今後同じ企業への応募を検討する別の求職者への情報提供のためだと理解し、快く協力しました。
面接記録はその日のうちに作成し、翌日には新しい企業の面接に臨むというサイクルを回す必要があったため、効率化が不可欠でした。
そこで、面接後の記憶が新しいうちにChatGPTに概要を口述・入力し、質問と回答を整理してもらう方法を取りました。音声入力が便利でした。これにより、記録は短時間で正確に仕上げられ、M氏に即日送付することができました。結果として、「面接 → 記録作成 → 翌日の面接準備」というリズムが安定し、複数社の面接を連続して行う中でも質を落とさずに対応できました。
こうして、私は複数社の面接を経て、最終的にある関西のインフラ系企業へと心を傾けていくことになります。
それは単に条件が合ったからではなく、「この企業であれば、私の経験と価値観を活かしつつ、長く働ける」という確信を得られたからです。
第4章:最終決断と新たな一歩
複数社の面接を経て、候補企業は次第に絞り込まれていきました。
最終段階に残ったのは、いずれも関西を拠点にし、私の経験を活かせるポジションを提示してくれた企業ばかりです。その中で、私は条件面だけではなく、面接を通じて感じた相性や将来の働き方を重視しました。
最終的に比較検討した企業はいずれも優良な条件を提示してくれましたが、その中でも特に印象的だったのが、ある関西のインフラ系企業でした。
選定の決め手
この企業を選んだ理由はいくつかあります。
勤務地が大阪に限定されることが明確だった
他社では「原則大阪」としながらも、プロジェクトによっては短期出張や他拠点対応の可能性が残るケースがありました。しかし、この企業は「本人の意志に反する転勤はさせない」と明言しており、介護事情を抱える私にとって安心感がありました。
鋼橋分野の知識・経験をそのまま活かせるポジション
面接でのやり取りから、入社直後は○○チームに配属され、やがて管理的な役割や若手育成にシフトしていくプランが描かれていました。これは、施工計画や現場管理で培った知識を最大限に活かせる流れでした。
定年後の再雇用条件の良さ
定年は60歳または62歳ですが、再雇用制度が整備されており、再雇用後の給与水準も8〜9割程度が見込めるという説明がありました。年収が半減するような厳しい条件ではなかったことも安心材料になりました。
一次面接で感じた人柄と安心感
一次面接では、所属予定部署のグループ長と、その上位にあたる部門長が対応してくれました。お二人とも実直で温かみのある雰囲気を持ち、私を「これから預かる人材」として受け止めてくれるような安心感がありました。
別の企業では「働かない50代はいらない」というような強い言葉をかけられる場面もありましたが、この企業ではそうした刺々しさはなく、穏やかで信頼できる空気を感じ取ることができました。
企業文化と面接での誠実な対応
面接官の質問は厳しさと温かさを併せ持っており、現場感覚を重視する姿勢と、技術者を大切にする社風が感じられました。質問の中には私の価値観や仕事観を深掘りするものが多く、それだけ「人を見て採用する」という意思を強く感じました。
内定までの過程
そして迎えた最終面接は、2025年6月中旬に本社にて対面で実施されました。面接官は計4名。役員クラスが揃う緊張感のある場でしたが、冒頭から社長や専務をはじめとする3名の役員は、緊張を和らげるような雰囲気で接してくれました。
質問は、これまでの経歴や退職理由、志望動機など、私の考えや経験を深掘りする内容が中心でした。特に、架設計画への対応方針や鋼橋以外(PC橋・RC橋)への関与姿勢、勤務地限定勤務の可否、年齢による職場適応、会社文化への順応姿勢など、今後の業務適応に直結するテーマが多く取り上げられました。私は正直に自分の得手不得手を示しつつ、「徐々に対応していきたい」「若手への助言や知識共有は積極的に行う」と回答しました。
面接の終盤では、緊張度の変化を尋ねられ、「入室時100%→面接中70%→退出時50%→終了後40%」と冗談交じりに答え、場が和みました。役員の方々は人当たりの柔らかい印象でしたが、ある部長は時折厳しい表情で私の反応を観察していたように感じました。これは、おそらく私の受け答えの中での柔軟性や反応力を見極めるためだったのでしょう。
こうしたやり取りを経て、面接終了後には手応えを感じつつ、本社1階で待機してくれていたM氏へ報告しました。M氏からは「おそらく良い返事がくるはずです」との言葉をもらい、その約20分後、正式に内定通知を専務から受け取ることができました。
内定受諾の決断
他社からも内定や最終面接の案内をいただいていましたが、私は迷いなくこの企業への入社を決めました。内定通知を受領した直後に即答しました。
条件面の満足度だけでなく、「この企業なら自分の価値を発揮できる」という確信を持てたことが大きかったのです。転職活動を始めた当初は、「今の年齢での転職はリスクが高いのではないか」という迷いがありましたが、家計管理や将来資金のシミュレーションを行い、M氏やChatGPTをはじめとするサポートを活用したことで、納得感を持って決断できました。
新しい職場への期待
入社後は、これまでの現場感覚と技術知識を社内に浸透させることが期待されています。その後、若手技術者の育成や業務改善にも携わる予定です。
「自分が経験してきたことを、次の世代にどう残すか」――これが、私にとって新たなミッションになります。
こうして私は、長い選考と準備を経て、新しいスタートラインに立つことになりました。
この決断に至るまでの一連のプロセスは、偶然の積み重ねではなく、計画的な情報収集と判断、そして人とのつながりによって形作られたものでした。
第5章 内定後の判断と入社決定までの経緯
内定通知を受け取った時点で、私は他にもいくつか選考が進んでいる企業がありました。しかし、最終的な判断は迷いませんでした。決め手は、これまでの面接を通じて感じた企業文化の柔らかさと、私の専門性を活かしつつ成長できる余地があるという確信です。
また、定年が60歳または62歳であっても再雇用制度が整備されており、しかも再雇用後の年収が大きく下がらない(退職時年収の8~9割程度になる可能性が高い)という条件も大きな安心材料でした。私は65歳まで必ず働き続けたいというよりも、60歳や62歳の節目で自身や家族の状況を見直し、その時点での最適な働き方を選べる余裕を求めていました。その意味で、この企業の制度設計は私の価値観と合致していました。
エージェントのM氏も、私の判断を全面的に支持してくれました。M氏は、他社との条件比較や面接日程の調整、企業側への質問確認など、最後まで手厚くサポートしてくれ、結果的にスムーズに意思決定することができました。
M氏からは「これで本当に良い転職になると思います」という言葉をもらい、私自身もこの数か月間の活動を振り返って、迷いなく頷くことができました。これまでの経験や努力が報われた瞬間であり、新たなスタートラインに立った実感がありました。
第6章 退職手続きと今後の資金手続きの準備
内定を受け取ったのは、これまでの努力が実を結んだ瞬間でした。内定連絡の翌々日には、早速上司に退職の意思を説明しました。上司からは引き留めの言葉もあり、しばらく時間をかけて話し合いを重ねましたが、最終的には私の考えを尊重していただけることになりました。円満に合意できたことは、大きな安心材料となりました。
引き継ぎについては、ChatGPTの力を借りる必要はありませんでした。これまで自分が携わってきた業務内容や段取りはすべて自分の頭の中にあり、現場で培った経験と記録を基に、自分の手で引き継ぎ資料を作成しました。現場の知識やノウハウを正確に後任へ渡すことを第一に考え、細部まで抜け漏れのないように仕上げました。
また、この退職を機に重要だと感じたのは、退職金に関する税金の確認でした。退職金は大きな金額になるため、税額計算の方法や控除の適用条件に間違いがないか、改めてチェックしました。これはリベシティで学んだ知識が非常に役立ち、安心して進めることができました。
さらに、企業型確定拠出年金(企業型DC)の移管手続きについても意識するようになりました。新しい職場がどの金融機関の企業型DCを採用しているのかはまだ不明で、その内容によっては、企業型DCへ移管するのか、あるいは個人型のiDeCoに移管するのかを判断する必要があります。この点についてはChatGPTを活用し、移管の仕組みやメリット・デメリットを事前に把握しておいたことで、スムーズに選択肢を整理できる状態にあります。
こうして、退職と同時に必要となる資金関連の手続きにも目を配りながら、新たなスタートへ向けて静かに準備を整えていきました。
第7章 転職活動を通じて学んだこと・感じたこと
今回の転職活動を振り返ると、きっかけは2024年11月にリベシティへ入会したことでした。入会後は家計管理やインデックス投資を本格的に学び、日々の家計簿の整備や資産状況の把握を進めていきました。また、両学長の動画を視聴し、毎朝配信される「朝の講義」も欠かさず視聴しました。こうして金融知識や生活設計の基礎を固める中で、将来に向けた選択肢が具体的に見えるようになっていきました。
家計管理を続けた結果、年収が900万円程度に下がっても生活の質を保てるという事実が明らかになりました。これが大きな安心材料となり、「収入よりも働き方を優先する」という判断軸を持って転職活動に臨むことができました。そして2025年4月3日、両学長の「転職活動はやってみるべき」というアドバイスに背中を押され、転職活動を始める決意を固めました。
結果として、働き方の改善だけでなく、現在の年収と同等か、むしろわずかに上回る水準のオファーを得られる見込みとなりました。年収面と生活面の双方で納得できる結論を得られたのは、家計管理で得た数字的な裏付けと、自分の市場価値を客観的に知る機会を作ったことが大きいと感じています。
また、活動を通じて学んだのは「情報の整理」と「行動の継続」の重要性です。求人票や面接内容をExcelで一覧化し、条件ごとに評価をつけることで、自分の意思決定がクリアになりました。さらに、面接ごとの記録作成やフィードバックを欠かさず行うことで、回を重ねるごとに受け答えの精度も上がりました。
加えて、企業の雰囲気や人柄の重要性も再認識しました。条件面だけでなく、面接で感じた誠実さや実直さ、安心して働ける空気感は、長期的なキャリア満足度を大きく左右する要素です。今回の転職活動では、そうした面まで比較検討できたことも大きな成果でした。
今回の経験は単に新しい職場を見つけるためだけでなく、「自分を知る」ためのプロセスでした。数字で裏付けられた生活設計、客観的に測った市場価値、人や組織との相性。この3つが揃ったことで、迷いのない決断ができ、働き方も収入も理想的な形で両立できたと確信しています。
リベシティに出会えたことがきっかけです。両学長の言葉が胸に刺さりました。ありがとうございます。とても感謝しています。
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
「今日が人生で一番若い日!!」
m(_ _)m
付録1:活動時系列(2024年11月〜2025年)
2024年11月
リベシティ入会。家計管理とインデックス投資を開始。両学長の動画視聴や朝の講義を毎日継続。
2024年12月〜2025年3月
家計簿の整備、資産状況の可視化、将来シミュレーションを実施。
年収900万円でも生活が成り立つことを確認。
2025年4月4日
転職活動開始を決意。エージェント登録、求人情報収集開始。
4月中旬
求人票をExcelに整理。条件ごとに〇△×で評価。
5月上旬〜下旬
書類選考通過企業が増え、面接準備を開始。ChatGPTを活用して志望動機や想定問答を作成。
6月初旬(6/4~6/10)
6社の一次面接を実施(オンライン2社、対面4社)。
面接記録を即日作成し、エージェントへ送付。
6月中旬〜下旬
最終候補を2社に絞り込み、最終面接を実施。
6月23日
第一志望企業の最終面接を実施。
6月23日(最終面接直後)
内定を受諾。退職手続きを開始。
2025年8月31日
現職退職予定日。
2025年9月1日
新職場入社予定日。
付録2:使用ツール一覧(転職活動で活用した主なツール・サービス)
リベシティ
・家計管理、投資、転職活動に関する知識を習得
・動画視聴、朝のライブ講義参加
ChatGPT
・求人票の要点整理(PDFからテキスト抽出後に貼り付け)
・Excel表作成のための条件整理(〇△×評価用コメント)
・志望動機や職歴説明文のブラッシュアップ
・面接想定問答集の作成
・音声リアルタイム機能による模擬面接練習
・面接記録の整理・文章化
Excel(Microsoft 365)
・求人情報・条件比較表の作成
・年収・条件のスコアリング管理
JACリクルートメント(転職エージェント)
・初期登録エージェント。求人紹介、面接調整、条件交渉
・面接記録提供の依頼を受け、活動履歴の共有に協力
第2エージェント(名称非公開)
・複数エージェント利用による比較と求人情報拡充
PDFリーダー/コピー機能
・求人票(PDF)のテキスト抽出用