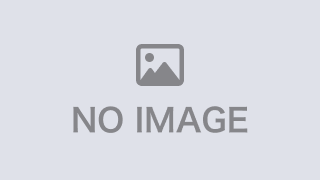- 投稿日:2025/06/05
- 更新日:2026/02/17

 ① はじめに(導入)
① はじめに(導入)
私は今でこそ読書が趣味となり学長おすすめ書籍を読み漁るほどになっているのですが(笑)、小さい頃は読書や作文がとても苦手でした。 特に読書感想文となると「何を書けばいいの?」と頭を抱え、泣きたくなることもしばしば……。 夏休みの課題が憂うつだったのを、今でもよく覚えています。
そんな自分だったからこそ、我が子には同じような思いをさせたくないという気持ちが強くありました。 「本を読むって、楽しい」そんな感覚を小さいうちから育んでもらいたい。 読書を「勉強の一環」としてだけではなく、「自然と手に取る習慣」にしてほしい。 そう思って、私は少しずつ、子どもたちに合った読書との関わり方を模索していきました。
今では、子どもたちと一緒に本を読む時間が何よりも大切なひとときになり、 本は人生を豊かにしてくれると心から実感しています。
今回は我が子たちがどのようにして読書を習慣化してきたのかを、ご紹介したいと思います。
この記事が、「どうすれば子どもに読書を好きになってもらえるのかな?」と悩んでいる親御さんの、少しでも参考になれれば嬉しいです。
② 家庭で行ってきた読書習慣の取り組み・工夫
本を好きになるには、「楽しい」と思える経験の積み重ねが大切です。 わが家では子どもたちの成長に合わせて、無理のないペースで読書との関わりを深めていきました。
◆ 読み聞かせ期(幼児〜年長)
■「読んで」と言われたら、いつでもOK
「今忙しいからあとでね」ではなく、できるだけ応じるようにしていました。 子どもが自分から興味を示してくれた瞬間を大切にしたかったんです。
■ 毎日2冊以上を習慣に
最初はその日の気分で読んでいましたが、だんだん毎晩のルーティンに。 気が付くと寝る前の読み聞かせは、親子にとって特別な時間になっていました。
■ 図書館をフル活用
絵本って意外とお金がかかるんですよね💦 だからこそ図書館をフル活用することで、いろんな本に出会えるようにしました。 週末の図書館通いは、子どもとの楽しみなイベントにもなっています。
■ 年齢に合わせた本の選び方
2〜3歳のころは、イラストや音の面白さを重視。 何十回も同じ本を読むこともしばしば。 4〜6歳くらいからは、ストーリー性のある絵本もどんどん取り入れました。 少し背伸びした本にチャレンジすることで、ぐっと集中する姿が増えていきました。
■ 読みながらの声かけ
ただ読むだけではなく、「この子は誰かな?」「どう思った?」など 途中で問いかけを入れるようにしていました。 会話が生まれることで理解も深まり、聞く姿勢にも変化が出てきました。
◆ 自読のスタート(年長〜小学校低学年)
■ 読めるようになったら「自分で読む」へ
ひらがな・カタカナが読めるようになってきた頃から、少しずつ自分で読むことに挑戦。 最初は文字数が少ない絵本から、徐々に文章が多い本へとシフトしていきました。
■ 「寝る前の読書」を習慣に
自読が慣れてきてからは、「毎晩1冊、必ず読む」を親子で約束しました。自然と毎日のルーティンとなり、本を読むことが生活の一部に。
■ 読書中は親が「聞き役」に
読んでいるときに、少し詰まっても手助けは最小限に。 最後まで読めたときには「よく読めたね」としっかり褒めてあげます。
■ 読後に「内容を話す」時間
読み終わった後、「誰がでてきた本かな?」「どんなことが起きたのかな?」「それで〇〇ちゃんはどう思ったのかな?」と聞くようにしました。 この対話が理解力や集中力アップにつながっているのではないかと思います。
③ 読後の対話へのステップ
読書が習慣になってきたら、次のステップは「読んだ内容を話すこと」。
この「話す→考える→自分の気持ちを言葉にする」という流れが、読解力や表現力を育ててくれると感じています。
とはいえ実際には、「感想を言ってみて」と言っても、子どもはなかなか言葉が出てきませんよね。私も大の苦手だったので、その気持ちは良くわかります。子どもたちも最初はうまく話せず、モジモジ……という場面がよくありました。
だからこそ、大切にしてきたのが 「問いかけ」でした。
📗 親が問いかけ役になる
「誰が出てきた本かな?」「どんなことが起きたのかな?」「それで〇〇ちゃんはどう思ったのかな?」
まずは、簡単な問いかけからスタート。
このとき「正解を言わせる」のではなく、「自分の言葉で話す経験」を積ませることを意識しました。
📕 学年に合わせて話す内容を調整する
長男(小3)と次男(小1)とでは、話してもらう内容のレベルを少し変えるようにしています。そうすることで、学年が上がるごとに自然とステップアップできる形にしました。
「どんな内容を話せるようになるとよいか?」は、ChatGPTに相談しながらテンプレートを作るのもおすすめです♪ 「誰が出てきた?」「何が起きた?」「どんな気持ちだった?」など、質問を順に重ねていくだけで、自然と会話形式で内容を整理することができます。
「誰が出てきた?」「何が起きた?」「どんな気持ちだった?」など、質問を順に重ねていくだけで、自然と会話形式で内容を整理することができます。
④ 好きになる・習慣化するための工夫
読書を「好きになる」「習慣にする」には、やっぱり無理なく楽しく続けられることが大切です。 我が家では、「毎日少しずつでも本とふれあう」というリズムを大事にしてきました。
◆「読む=楽しい」と感じられる仕掛けを
・寝る前に読む時間を「楽しみ」にする(お気に入りの本を一緒に選ぶ)
・読んだ後に感想を話すことで、親子の会話が自然に広がる
・お気に入りキャラクターやシリーズ本で「続きが気になる!」を演出
「読まされている」のではなく、「自分から読みたい」という気持ちを育てるのがポイント。
◆ 親も一緒に読む・読む姿を見せる
「パパも読んでるから、自分も読もう」
子どもは親の姿をよく見ています。
なので、私自身も、
・子どもたちの前で読書をする
・本をリビングなど身近な場所に置く
など、本を「身近な存在」に感じてもらえるように工夫をしています。
◆ 気分が乗らないときはムリしない
「今日は読みたくないな〜」なんて日ももちろんあります。 そんなときは無理に読ませず、「じゃあ明日は一緒に読もうね」と声をかけるようにしています。
◆ 年間読書数の目標を決めてモチベーションアップ
「今年は◯冊読もうね!」と親子でゆるく目標を決めることで、楽しみながら継続できます。達成感が味わえることで、「読書=頑張った証」として自信にもつながります✨
ちなみに、今年の長男と次男の目標は「年間100冊」。なんと、5月28日にはすでに達成! 🎉
今では「読書記録をつける!」とさらに張り切っていて、その様子に成長を感じています。
⑤ 子どもの変化・成長
少しずつ読書を続けていくなかで、子どもたちに確かな変化が見えてきました。ふとした会話の中で、「あれ?こんな言い回しどこで覚えたんやろ?」と思うことが増えました。本の中で出会った言葉や表現を、自然と使っていたんですね。
また、感想を話すときも、「楽しかった!」だけじゃなく、 「〇〇の場面がおもしろかった」「〇〇くんの気持ちがわかった」など、自分の気持ちを表現する力が育ってきたなと感じます。
⑥ おわりに(まとめ・エール)
「うちの子、あんまり本を読まへんのよなあ…」
「どうやったら読書が好きになってくれるんやろ?」
そんなふうに悩んでたのは、まさに昔の私自身でした。
でも今は、「毎日ちょっとずつ、本にふれる時間があるだけでええんやな」と思えるようになってきました。
📘 読書のスタートは、“読み聞かせ”からで十分。
📙 読む量よりも、“楽しめたかどうか”を大事にしたい。
📗 そしてなにより、子どもの“できた!”をいっしょに喜んであげること。
これが、私たち家族が歩んできた読書習慣づくりの道のりです。
この記事が、「どうすれば子どもに読書を好きになってもらえるのかな?」と悩んでいる親御さんの、少しでも参考になれたのなら、とても嬉しいです。